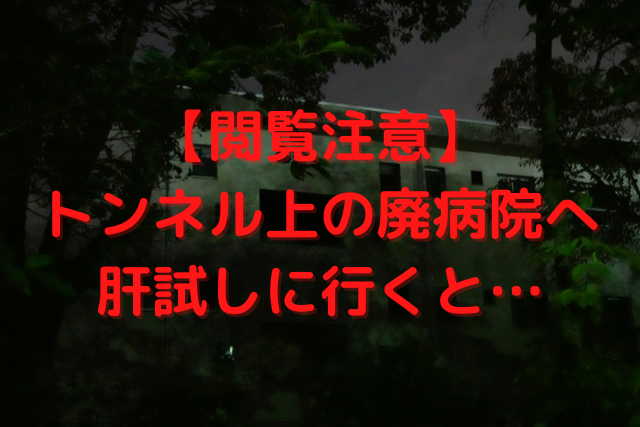「ちょっとわかんない。多分何もいないけど、もう帰ったら?ねえ?きいてる?」
Aはもはや聞いていない。
「その部屋なんっもなくてさ、まぁ入り口から見ただけなんだけでわかんねぇけど、赤のペンキが塗りたくってあった。
部屋のどこまでそうなのかはわかんない。遠目に一瞬だけ見てすぐに帰ってきた。
流石に入れなかったよ、怖すぎ。無理無理。なにも出来ない。
Sに聞いたら、天井まで身長が届いて、首を少し傾げてる、髪ぼっさぼさの女がつったってたってさ。
部屋の奥にね。俺の方振り向こうとした瞬間、俺がにげたんだってさ。
Sにも悪い事したよ。暫くうなされたって。カクカクした声が聴こえるんだってよ」
Aが語り終えた。なんだか死にに行く様な感じがしてきた。
「とにかくさ、お前が行きたいって言った理由の一つは潰したよ。あそこに綺麗な部屋なんか無い」
「つかおかしいんだよ、あんなところに病院がある事自体。
この辺に俺たちの団地以外住宅は無いじゃん?ほんの数十年前に山を切り開いて、ベッドタウンにしたわけだ。
トンネルだってそうだろ。どのタイミングで病院が建って、いつの間に廃墟になるの?
あんなとこに、だれがはるばる診察に行ってたんだよ」
Aが興奮気味になってきた。
「正直、行きたく無い。いまんとこ俺たちには何も無いし、直接は気味悪い部屋見ただけだから良いけど……。
別に死ぬのはあんまり怖くないし。でもあそこで死ぬのは絶っ対……嫌」
自分でもどうしたいのかわからなくなっていた。
「ぁ、へんな金髪野郎!」Sが入ってきた。本当に偶然今来たらしい。
「おっきくなったなぁー。つか、よく覚えてんなw」少し場が和んだ。
Sは今高校生で、えらくポップでおしゃれになっていた。
「あそこ行こうとしてんでしょ?やめときなよ」
急に真顔になって、ベッドに座り込む。